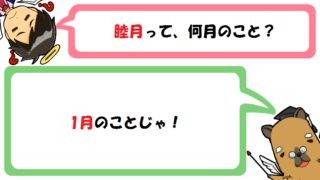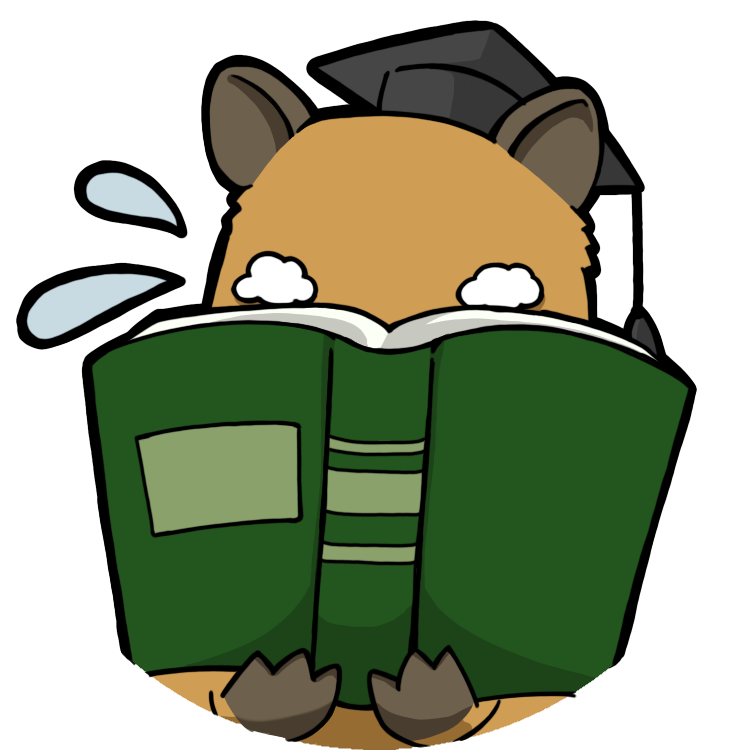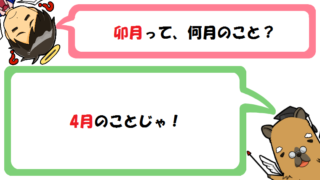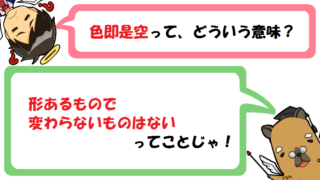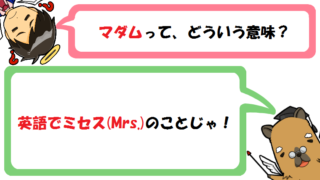弥生は旧暦の何月?意味/読み方/由来とは?3月の時候の挨拶と季語も紹介!弥生の意味や読み方とは?弥生は旧暦の何月?弥生は現在の暦でいつからいつまでの時期?なぜ弥生なのか由来(語源)を解説!3月上旬・中旬・下旬の時候の挨拶も例文で紹介!季語を使ってオリジナルの時候の挨拶を作ろう!
弥生は旧暦の何月?読み方と意味は?

今日は、弥生について解説していきましょう\(^o^)/
読み方は「やよい」。
陰暦(旧暦)の3月のこと。
まず、弥生の読み方は「やよい」です。
弥生は、陰暦(旧暦)の3月を指す言葉です。
弥生を現在の暦に当てはめると、3月下旬~5月上旬ごろの時期になります。
便宜上、現在の暦の3月を「弥生」と呼ぶことがあります。
「陰暦」とは、月の満ち欠けの周期を基にした暦のことで、1ヶ月は約29.5日です。
日本では、明治6年に陽暦が採用される以前に陰暦が使われていたため、陰暦を「旧暦」と呼ぶ場合もあります。
ちなみに現在、日本を始めとした世界の多くの国で使われているのは「太陽暦」で、地球が太陽の周りを回る公転周期を基にした暦です。
日本では、太陽暦を「新暦」と呼ぶこともあります。

弥生の由来(語源)は?

漢字の「弥(いや)」は、「いよいよ」「ますます」の意味です。
また「生(おい)」は、「生い茂る」などと使うように、草木が芽吹くことを表します。
3月は冬が終わっていよいよ草木が生い茂る春の季節です。
草木がだんだん芽吹く月という意味の「木草弥や生ひ月(きくさいやおひづき)」が詰まって「弥生(いやおい)」→「弥生(やよい)」と変化したのが由来です。
3月の時候の挨拶と季語も紹介!

手紙に使える3月の時候の挨拶も紹介していきましょう\(^o^)/
時候の挨拶は季節を表す言葉を用いた文章のことで、相手の健康や安否を気遣う意味があります。
3月上旬~中旬の時候の挨拶
3月上旬~中旬の「時候の挨拶」+「安否の挨拶」の例文です。
まだ肌寒い日もありますが、暖かさを感じる日も増えてくるので、そのことを盛り込むと良いでしょう。
<ビジネス向け>
「浅春の候、貴店ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。」
「春寒の候、皆様にはお元気でお過ごしのことと存じます。」
「向春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。」
「早春の候、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。」
<カジュアルに>
「寒かったり暖かかったりの毎日ですが、お元気でお過ごしのことと存じます。」
「寒さも一段落し、桃の花が目に鮮やかな頃となりました。お変わりありませんか。」
「少しずつコートも不要な季節となってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。」
「桃の節句も過ぎ、うららかな春の日が続いております。」
3月中旬~下旬の時候の挨拶

3月中旬~下旬の「時候の挨拶」+「安否の挨拶」の例文です。
「暑さ寒さも彼岸まで」といわれる春分は、3月21日ごろ。
日に日に濃くなっていく春の気配を楽しんでいる気持ちが伝わるような文章にしたいですね。
<ビジネス向け>
「春暖の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。」
「春風の候、ご家族の皆様には、お健やかにお過ごしのことと拝察いたします。」
「春分の候、ご一同様には、ますますご壮健のことと存じます。」
「麗日の候、〇〇様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。」
<カジュアルに>
「桜の開花が待たれる頃となりました。お変わりなくお過ごしでしょうか。」
「花の便りが聞かれる頃となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。」
「桜前線の待ち遠しい今日この頃、たくさんお花見できそうですか?」
「春うらら、穏やかな毎日を過ごされていることでしょう。」
3月の季語は?

時候の挨拶は、季語を入れて季節感を出すのがマナーです。
3月の季語をいくつか紹介するので、手紙を書くときの参考にしてくださいね♪
仲春、彼岸、啓蟄、春風、余寒、春雨、花冷え、春一番、雪解け、
残雪、水温む、春の川、雛祭り、雛遊び、白酒、雛あられ、
お彼岸、お墓参り、ぼたもち、卒業式、入学式、新入社員、朝寝、
春休み、梅、桃、桜、たんぽぽ、つくし、菜の花、よもぎ、れんげ、
草の芽、芽吹く、木の芽、若草、わらび、ぜんまい、うぐいす、
つばめ、ひばり、鰆、蛤、蝶、ホワイトデー、花粉症、など
時候の挨拶は、その季節を感じられる言葉を選べば、どんな表現でも構いません。
ぜひ、季語を使ってあなたらしい時候の挨拶を作ってみましょう!
弥生について、最後まで読んでいただきありがとうございました!
新しい環境で心機一転、皆さまの幸福をお祈りいたします\(^o^)/