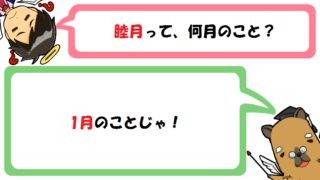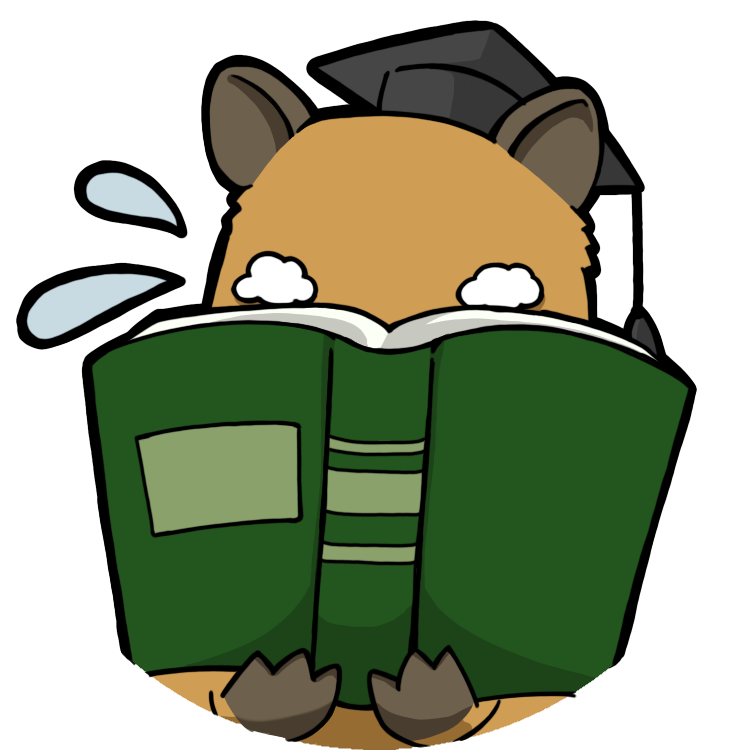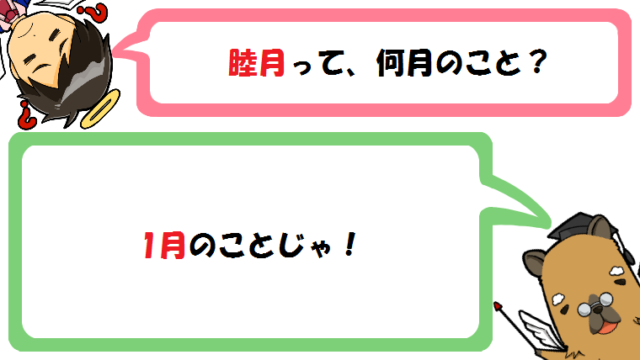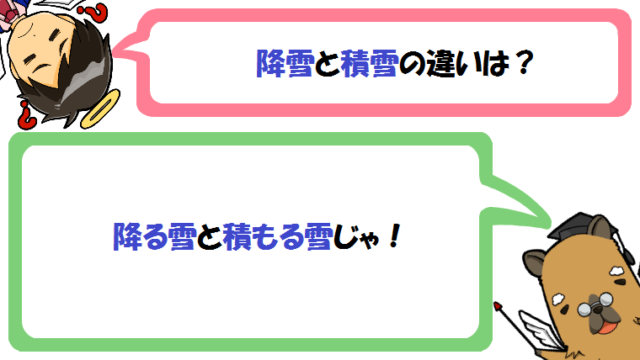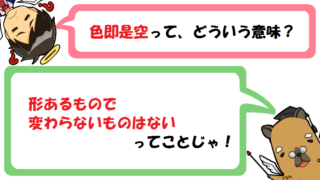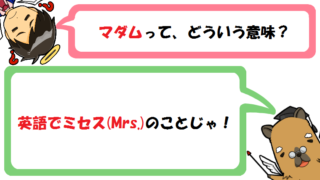陰暦とは?太陽暦/旧暦/新暦との違いは?月の名前(異称)と語源を一覧で紹介!陰暦とは何?陰暦は昔のカレンダーのこと?陰暦と太陽暦・旧暦・新暦との違いは?太陽暦は陰暦の対義語?旧暦や新暦って?陰暦の月の名前(異称)と語源を一覧で紹介!陰暦についてわかりやすく解説します!
もくじ
陰暦とは?

ニュースで「暦の上ではもう春です」と聞いたり、手紙で「師走の候」を見たりすることがありますね。
今日は、陰暦について解説していきましょう\(^o^)/
読み方は「いんれき」。
「太陰暦(たいいんれき)」とも呼ばれる。
月の満ち欠けの周期を基にした暦のこと。
陰暦は、新月から新月までの月の満ち欠けを基にした暦です。
1ヶ月が約29.5日のため、1年は約354日になります。
太陽暦の1年が365日なので、陰暦のカレンダーは季節がだんだんズレてきてしまいます。
ズレが1ヶ月分くらいになると、「閏月(うるうづき)」を入れて修正するのです。
陰暦と太陽暦・旧暦・新暦との違いは?

太陽暦は陰暦の対義語?
読み方は「たいようれき」。
「陽暦」や「グレゴリオ暦」とも呼ばれる。
地球が太陽の周りを回る周期を基にした暦のこと。
太陽暦は、地球が太陽の周りを回る公転周期を基にした暦です。
正確には、公転周期は365.2422日のため、4年に一度、一年を366日とする「閏年(うるうどし)」を入れます。
旧暦とは?
読み方は「きゅうれき」。
現在の暦法に替える前に使われていた暦法のこと。
明治6年に太陽暦が採用される以前の日本では、陰暦が使われていたため、陰暦のことを旧暦と呼ぶ人もいます。
日本においては、「陰暦=旧暦」と捉えても問題ありません。
新暦とは?
読み方は「しんれき」。
改暦が行われた場合の改暦後の暦法のこと。
日本では陰暦から太陽暦に改暦したため、太陽暦が新暦となります。
日本においては、「太陽暦=新暦」と捉えても問題ありません。
陰暦と太陽暦・旧暦・新暦との違い

陰暦と太陽暦・旧暦・新暦との違いを見ていきましょう\(^o^)/
陰暦(太陰暦):月の周期に基づく暦法
陽暦(太陽暦):太陽の周期に基づく暦法
旧暦:現在の暦法に替える前に使われていた暦法
新暦:改暦が行われた場合の改暦後の暦法
ちなみに現在、日本を始めとした世界の多くの国で使われているのは「太陽暦」です。
陰暦(太陰暦)と陽暦(太陽暦)、旧暦と新暦はそれぞれ対義語です。
日本では、陰暦=旧暦、太陽暦=新暦と覚えておきましょう!
陰暦の月の名前(異称)と語源を一覧で紹介!
月の異称(名前)はとても昔から使われており、「万葉集」や「日本書紀」などの古典にも登場しています。
その語源を見ると、現在の暦と一ヶ月ほどの季節のズレがありますので、注意して見ていきましょう\(^o^)/
1月:睦月(むつき)
 「仲睦まじい月」という意味で睦月です。
「仲睦まじい月」という意味で睦月です。
睦月は、お正月に家族や親戚が集まり、互いに仲良く親しみ合って「睦み合う(むつみあう)」ことが由来です。
そこから「睦び月(むつびつき)」→「睦月(むつき)」となった説が有力です。
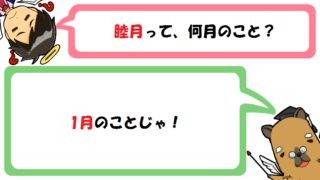
2月:如月(きさらぎ)

「着物を更に重ねて着る月」という意味で如月です。
如月は、寒さで衣(きぬ)を更に重ねて着る月ということで、「衣更着(きさらぎ)」が由来だとする説が有力です。
また、草木の芽が張り出す月で「草木張月(くさきはりづき)」の説もあります。

3月:弥生(やよい)

「草木が生い茂る月」という意味で弥生です。
漢字の「弥(いや)」は、「いよいよ」「ますます」の意味です。
また「生(おい)」は、「生い茂る」などと使うように、草木が芽吹くことを表します。
草木がだんだん芽吹く月という意味の「木草弥や生ひ月(きくさいやおひづき)」が詰まって「弥生(いやおい)」→「弥生(やよい)」と変化したのが由来です。
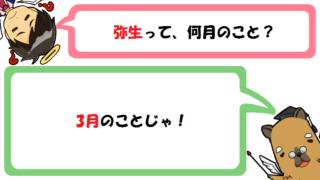
4月:卯月(うづき)

「卯の花が咲く月」という意味で卯月です。
卯月の由来は、卯の花が咲く季節なので、「卯の花月」を略した説が有力です。
また、十二支の四番目が「卯(うさぎ)」であることから、干支を月に当てはめた説もあります。
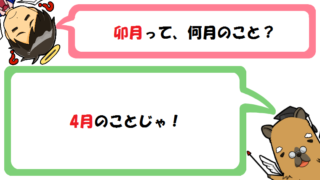
5月:皐月(さつき)

「稲の苗を作る稲作の月」という意味で皐月です。
皐月の「さ」は耕作や田植えを意味する古語で、稲作の月の「さつき」が由来です。
また、早苗を植える月の「早苗月(さなえづき)」が略されて「さつき」になった説もあります。
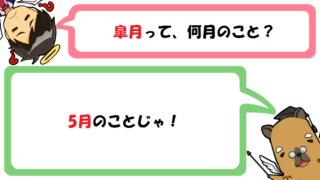
6月:水無月(みなづき)

「水の月」という意味で水無月です。
水無月の「無」は、現代語で「の」にあたる連体助詞の「な」で、「水の月」という意味だとする説が有力です。
陰暦の6月は田んぼに水を引く月なので、水無月と呼ばれるようになりました。
梅雨が明けて暑くなり、水が枯れて無くなる月だから「水の無い月」の説もあります。

7月:文月(ふみづき/ふづき)

「文を書く月」という意味で文月です。
文月の語源は、短冊に歌や字を書いて、書道の上達を祈った七夕の行事にちなんだ「文披月(ふみひらきづき)」が転じた説が有力です。
また、お互いの無事を確かめるために、便りや贈り物をして気持ちを伝えあっていたことが由来の説もあります。
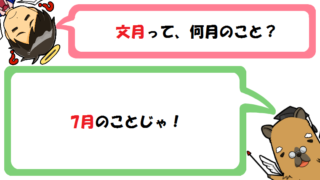
8月:葉月(はづき)

「葉が落ちる月」という意味で葉月です。
葉月の語源は、葉が落ちる月の「葉落ち月(はおちづき)」が転じて「葉月」となった説が有力です。
葉っぱが美しく色づき始める「紅葉の月」とする説や、稲穂が張る月で「穂張り月」が由来の説もあります。

9月:長月(ながつき)

「夜が長くなる月」という意味で長月です。
長月の語源は、夜がだんだん長くなる月で「夜長月(よながつき)」の略だとする説が有力です。
9月23日ごろの秋分の日を境に、徐々に夜の時間が長くなってきますね。

10月:神無月(かんなづき) ※出雲大社では神在月(かみありつき)

「神の月」という意味で神無月です。
神無月の「無」は、現代語で「の」にあたる連体助詞の「な」で、「神の月」という意味だとする説が有力です。
中世の俗説では、10月に全国の神々が出雲大社に集まり、各地に神がいなくなることから「神無月」になったとされています。
出雲の国(現在の島根県)では、反対に「神在月/神有月(かみありづき)」と呼ばれます。

11月:霜月(しもつき)

「霜が降りる月」という意味で霜月です。
霜月の語源は、秋も深まり早いところでは朝霜が降りる時期ということで、「霜降り月/霜降月(しもふりつき)」の略とする説が有力です。

12月:師走(しわす)

「師僧も走るくらい忙しい月」という意味で師走です。
年末は僧侶までもがお経をあげるために走り回るくらい忙しいから「師馳す(しはす)」となったのが由来です。

陰暦について、最後まで読んでいただきありがとうございました!
由来と合わせて、月の異名を全部覚えてみてくださいね♪