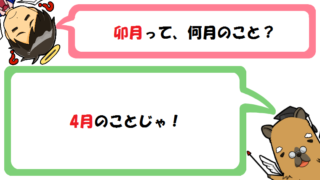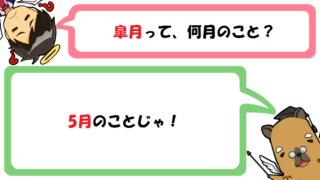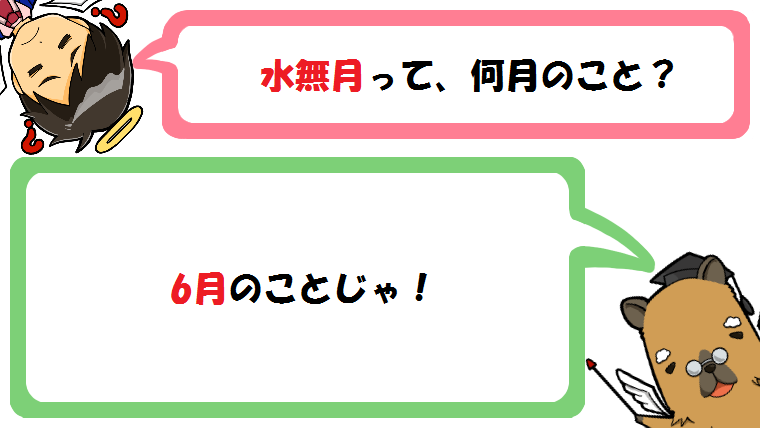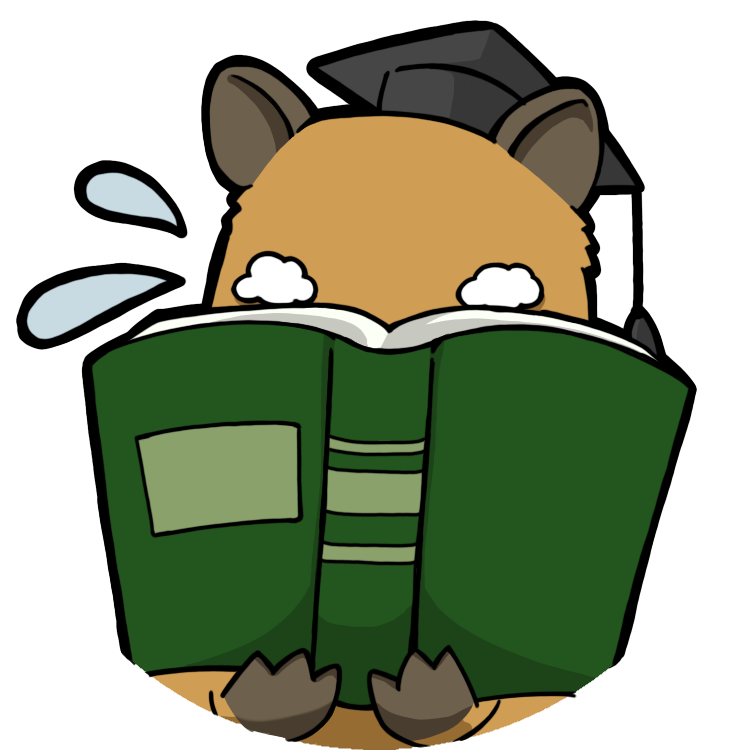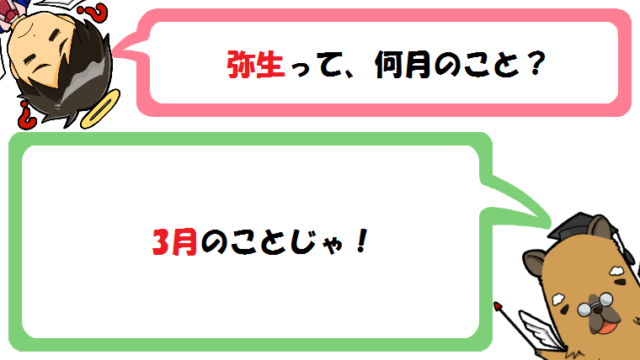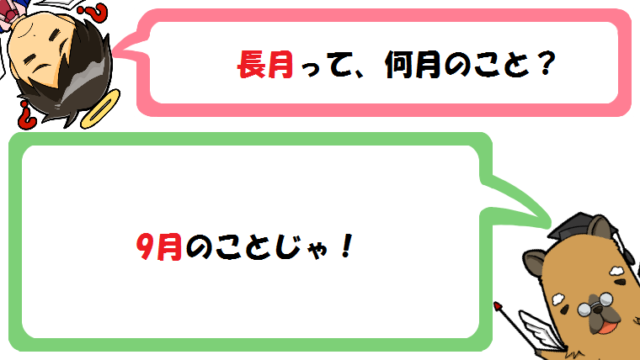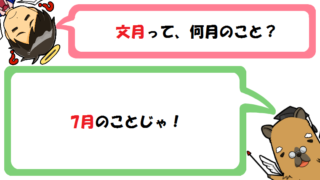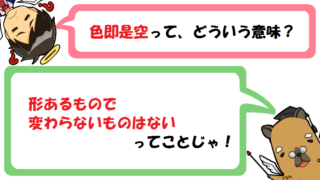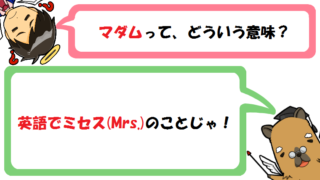水無月は旧暦の何月?意味/読み方/由来とは?京都の和菓子?6月の時候の挨拶と季語も紹介!水無月の意味や読み方とは?水無月は旧暦の何月?水無月は現在の暦でいつの時期?京都の和菓子でいつ食べるの?なぜ水無月なのか由来(語源)を解説!6月の季語と上旬・中旬・下旬の時候の挨拶も例文で紹介!
水無月は旧暦の何月?読み方と意味は?

今日は、水無月について解説していきましょう\(^o^)/
読み方は「みなづき」。
陰暦(旧暦)の6月のこと。
まず、水無月の読み方は「みなづき」です。
水無月は、陰暦(旧暦)の6月を指す言葉です。
水無月を現在の暦に当てはめると、6月下旬~8月上旬ごろの時期になります。
便宜上、現在の暦の6月を「水無月」と呼ぶことがあります。
「陰暦」とは、月の満ち欠けの周期を基にした暦のことで、1ヶ月は約29.5日です。
日本では、明治6年に陽暦が採用される以前に陰暦が使われていたため、陰暦を「旧暦」と呼ぶ場合もあります。
ちなみに現在、日本を始めとした世界の多くの国で使われているのは「太陽暦」で、地球が太陽の周りを回る公転周期を基にした暦です。
日本では、太陽暦を「新暦」と呼ぶこともあります。

水無月は京都の和菓子?いつ食べるの?

ちなみに、和菓子の「水無月」は、白いういろうの上に小豆の粒あんを散らして、三角形に切ったものです。
京都では、6月30日の夏越祓(なごしのはらえ)に、過ぎた半年の穢れを祓い、1年の残り半分の無病息災を願って食べる習慣があります。
三角形は氷のかけら、小豆には厄除けの意味があるとされています。
平安時代には、旧暦6月1日の「氷の節句」の日に氷を口にすると夏バテしないといわれており、氷室から氷を取り寄せて暑気払いをする宮中の風習がありました。
※氷室は、冬にできた氷を夏まで保存する自然の冷蔵庫のこと
しかし、氷は貴重なものなので庶民には手が届きません。
夏の暑さを乗り切ろうとして氷に似せて作った食べ物が「水無月」なのです。
水無月の由来(語源)は?

水無月の「無」は、現代語で「の」にあたる連体助詞の「な」で、「水の月」という意味だとする説が有力です。
陰暦の6月は田んぼに水を引く月なので、水無月と呼ばれるようになりました。
他にも、
- 田植えが終わって田んぼに水を張る月「水張月(みずはりづき)」が由来説
- 田植という大仕事を仕終えた月「皆仕尽(みなしつき)」が由来説
- 田んぼに水を引くので田んぼ以外に水が無いから「水の無い月」説
- 梅雨が明けて暑くなり、水が枯れて無くなる月だから「水の無い月」説
があります。
6月の時候の挨拶と季語も紹介!

手紙に使える6月の時候の挨拶も紹介していきましょう\(^o^)/
時候の挨拶は季節を表す言葉を用いた文章のことで、相手の健康や安否を気遣う意味があります。
6月上旬~中旬の時候の挨拶
6月上旬~中旬の「時候の挨拶」+「安否の挨拶」の例文です。
入梅や梅雨の言葉は、梅雨に入っていれば使います。
梅雨空が続いている場合は、夏の日差しを感じさせる向暑や初夏などの表現は避けましょう。
<ビジネス向け>
「初夏の候、平素は格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。」
「入梅の候、貴殿ますますご清祥の由、何よりと存じます。」
「向暑の候、ご家族の皆様には、お健やかにお過ごしのことと拝察いたします。」
「忙種の候、貴社におかれましては益々ご清栄の段、心よりお慶び申し上げます。」
<カジュアルに>
「梅雨がもうそこまでやってきておりますが、いかがお過ごしでしょうか。」
「梅雨晴れの一日、夏本番を思わせる強い日差しとなりました。皆様お変わりはないでしょうか。」
「梅雨空が続く毎日ですが、お変わりなくお過ごしでしょうか。」
「衣替えも終え、夏の装いが目につくようになりましたね。〇〇様にはお元気でお過ごしのことと存じます。」
6月中旬~下旬の時候の挨拶

6月中旬~下旬の「時候の挨拶」+「安否の挨拶」の例文です。
時候の挨拶は、手紙を送る相手に合わせるものなので、相手の季節感に合わせた表現を使いましょう。
<ビジネス向け>
「梅雨の候、貴社にはますますご隆盛の段、お慶び申し上げます。」
「夏至の候、ご家族の皆様には、お健やかにお過ごしのことと拝察いたします。」
「向暑の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。」
「霖雨の候、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。」
<カジュアルに>
「梅雨明けが待たれるこのごろですが、つつがなくお過ごしのことと存じます。」
「雨に濡れる紫陽花が美しさを増しています。皆様お元気でいらっしゃいますか。」
「このところ梅雨寒の日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。」
「梅雨前線が停滞し、今年の梅雨は長引きそうです。そちらはいかがでしょうか。」
6月の季語は?

時候の挨拶は、季語を入れて季節感を出すのがマナーです。
6月の季語をいくつか紹介するので、手紙を書くときの参考にしてくださいね♪
入梅、梅雨、衣替え、田植え、父の日、ジューンブライド、
あやめ、あじさい、かきつばた、しゃくなげ、鮎釣り、
鵜飼、うなぎ、なまず、かつお、あじ、いさき、蛍、
蛍狩り、かたつむり、かえる、あめんぼう、つばめ、など
時候の挨拶は、その季節を感じられる言葉を選べば、どんな表現でも構いません。
ぜひ、季語を使ってあなたらしい時候の挨拶を作ってみましょう!
水無月について、最後まで読んでいただきありがとうございました!
日増しに暑くなってきますが、お互い元気に爽快な夏を迎えましょう\(^o^)/