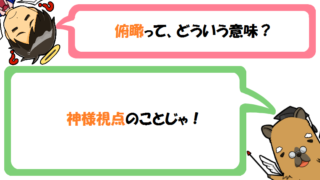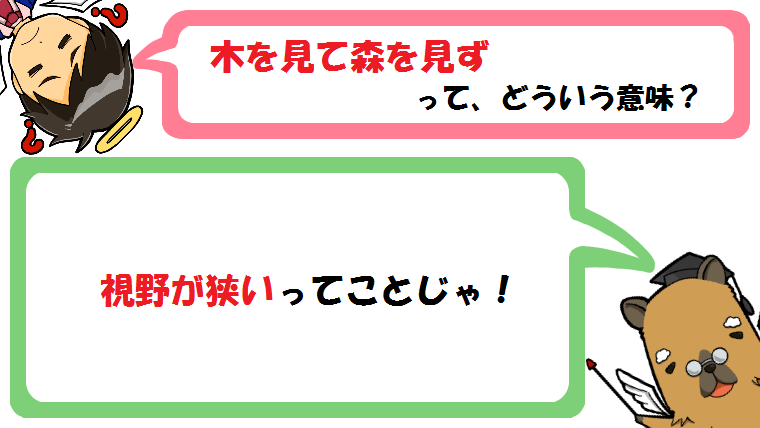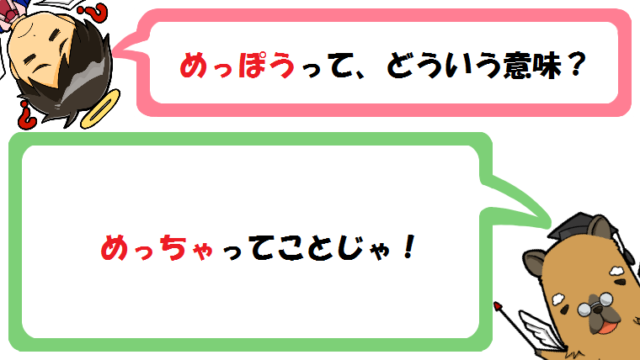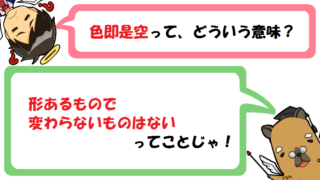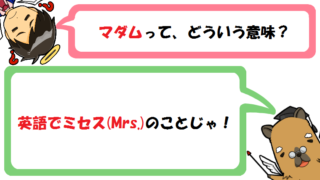木を見て森を見ずの意味とは?類義語と対義語は?語源や使い方(例文)も!木を見て森を見ずの意味は視野が狭いこと!?木を見て森を見ずの由来(語源)は?木を見て森を見ずの類義語は?木を見て森を見ずの反対語(対義語)は?木を見て森を見ずの英語は?木を見て森を見ずの使い方も例文で解説!
もくじ
木を見て森を見ずの意味とは?

ビジネスシーンで「木を見て森を見ずになっているよ」と指摘されたことはありませんか?
今日は、ことわざ・慣用句の木を見て森を見ずについて解説していきましょう\(^o^)/
物事の一部分に気を取られて、全体を見失うこと。
木を見て森を見ずとは、目の前のことや小さいことに心を奪われて、視野が狭くなっている様子を表す格言です。
一本一本の木だけを見ていると、森の全体像を見ることができないということから来ています。
仕事中に「木を見て森を見ずになっているよ」と注意された場合、あなたは些細なことにこだわりすぎて、物事の本質を見落としている可能性があります。
例えば、目先の利益を追い求めすぎて、会社全体を見渡せていない場合ですね。
ビジネスでは、目の前の仕事に集中することも大事ですが、時々一歩引いて、全体を俯瞰して見るのも大事です。
木を見て森を見ずの由来(語源)はフランス語?ドイツ語?

木を見て森を見ずの由来は、英語のことわざである、
「You cannot see the wood for the trees.(木を見て森を見ることはできない。)」
を日本語に訳したものです。
また、ヨーロッパにも同様に「木を見て森を見ず」という意味のことわざがあります。
フランス語:C‘est l’arbre qui cache la forêt.(木が森を隠す。)
ドイツ語:Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.(木のために森が見えない)
これらの外国のことわざが、日本に入ってきて「木を見て森を見ず」と定着しました。
英語、フランス語、ドイツ語のどのことわざが最初に日本に伝わったかはわかっていません。
木を見て森を見ずの類義語は?

ここでは、木を見て森を見ずの類義語を紹介します\(^o^)/
木を数えて林を忘れる
物事の一部分に気を取られて、全体を見失うこと。
木を数えて林を忘れるも、木を見て森を見ずと同じく、一部分を「木」、全体を「林」として、細部にこだわると全体を忘れてしまうということです。
金を攫む者は人を見ず
「金を掴むものは人を見ず」とも。
読み方は「きんをつかむものはひとをみず」。
一つのことに夢中になると、他のことが全く目に入らなくなること。
金を攫む者は人を見ずとは、金を盗って逃げた男が、役人に捕えられて尋問された際に「金しか見えずに、周りの人が見えなかった。」と答えたという中国の故事が由来です。
鹿を追う者は山を見ず
「鹿を逐う猟師は山を見ず」とも。
目先の利益を追っていると、周囲の状況に気づかないこと。
鹿を追う者は山を見ずとは、獲物の鹿ばかり見ていると、山全体を見渡すことができず、危険な目にあうという中国の故事が由来です。
獣を逐う者は目に太山を見ず
読み方は「じゅうをおうものはめにたいざんをみず」。
目先の利益を追っていると、周囲の状況に気づかないこと。
獣を逐う者は目に太山を見ずとは、鹿を追う者は山を見ずと同じく、獲物の獣ばかり見ていると、山全体を見渡すことができず、危険な目にあうという中国の故事が由来です。
木っ端を拾うて材木を流す
読み方は「こっぱをひろうてざいもくをながす」。
小さいことにこだわっていて、大きいことを失敗すること。
木っ端を拾うて材木を流すとは、木の切れ端を夢中になって集めていたら、大きな材木を流してしまうことから来ています。
菜園作りの野良荒らし
読み方は「さいえんづくりののらあらし」。
細かいことにこだわっていて、大きなことに手抜かりなこと。
菜園作りの野良荒らしとは、野菜の畑にかかりきりになり、肝心の米や麦を作る畑を荒れ放題にしていることから来ています。
木を見て森を見ずの反対語(対義語)は?

ここでは、木を見て森を見ずの反対語(対義語)を紹介します\(^o^)/
森を見て木を見ず
全体しか見ておらず、小さなことを見落とすこと。
木を見て森を見ずを反対にしたのが、森を見て木を見ずです。
意味もそのまま反対で、全体ばかり見ていて、詳細を見落とすことになります。
鹿を逐う者は兎を顧みず
読み方は「しかをおうものはうさぎをかえりみず」。
大きな利益を追う者は、小さな利益は問題にもしないこと。
鹿を逐う者は兎を顧みずとは、大きな鹿を狙っているものは、小さな兎には目もくれないことから来ています。
大行は細謹を顧みず
読み方は「たいこうはさいきんをかえりみず」。
大きなことを成し遂げようとする者は、ささいなことはこだわらずに、目標に向かって積極的に動くこと。
大行は細謹を顧みずは、中国の故事が由来です。
漢の沛公(はいこう)(後の漢の高祖劉邦(りゅうほう))が
楚の項羽(こうう)と鴻門(こうもん)で会ったとき、
宴会の途中で沛公は自分の命がねらわれているのを知った。
沛公が便所に立ったとき、側近の武将樊かい(はんかい)が、
そのまま逃げるように勧めたが、
沛公は項羽に別れの挨拶をしていないからと、ためらった。
そのときに樊かいが言ったことばである。
「大事を行う場合に小さな礼など問題にしない。
いま、相手は刀とまな板で、こちらは魚肉である。
どうして別れの挨拶などする必要がありますか」と。
こうして沛公は馬を駆って逃げ、九死に一生を得たという。出典:http://www2.odn.ne.jp/kotowaza/sub19-2-3-taikouha.htm
鷲は蠅を捕らえず
読み方は「わしははえをとらえず」。
大物は、小さな利益は問題にしないこと。
鷲は蠅を捕らえずとは、元々はギリシア語のことわざで、ワシのように大きい鳥は、小さなハエなど捕らないことから来ています。
大人は大耳
読み方は「たいじんはおおみみ」。
徳が高い立派な人は、聞く態度も大らかで、小さなことをいちいち耳にとめないこと。
小の虫を殺して大の虫を助ける
読み方は「しょうのむしをころしてだいのむしをたすける」。
小さなものを犠牲にして大きなものを助けること。
全体を生かすために、一部を切り捨てること。
木を見て森を見ずの英語は?

木を見て森を見ずの英語は、「You cannot see the wood for the trees.(木を見て森を見ることはできない。)」です。
「He can’t see the wood for the trees.(彼は木を見て森を見ずだ。)」
のように使います。
他にも、
- to be caught up with trivial matters and lose sight of the big picture
- be too involved in it to understand the situation clearly
- fail to see the big picture of it
- Failing to see the big picture.
- Penny wise, pound foolish.
と言い換えることができます。
木を見て森を見ずの使い方を例文で紹介!

木を見て森を見ずとは、物事の細部ばかり見ていて、全体を見失ってしまうことでしたね。
全体像を見渡せずに、視野が狭くなっている人に対して、「木を見て森を見ずになっているよ」と注意として使うことができます。
また、自分の視野が狭くて失敗してしまったときに「木を見て森を見ずだった」と反省するときにも使えます。
それでは、木を見て森を見ずの使い方を例文で紹介します\(^o^)/
「数円安い商品を買いに行くためにガソリン代を使うなんて、まさに木を見て森を見ずだ。」
「若い頃はチームの勝利よりも自分が活躍することしか考えておらず、木を見て森を見ずだった。」
「リーダーとして、木を見て森を見ずではいけないよ。」
「その帽子はセンスが良いが、全体としてのまとまりがなく、木を見て森を見ずだ。」
「木を見て森を見ずにならないように、もう一度プロジェクトの全体を見直してみよう。」
「今日の会議は木を見て森を見ずで、話しがまとまらなかった。」
「あまり自分の仕事ばかり考えていると、木を見て森を見ずになってしまうよ。」
木を見て森を見ずについて、最後まで読んでいただきありがとうございました!
木を見るのも、森を見るのも大事なので、複数の視点を持てるようになりたいですね。