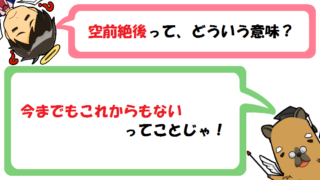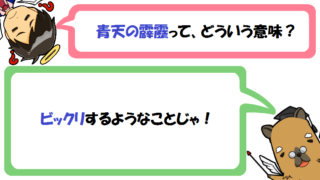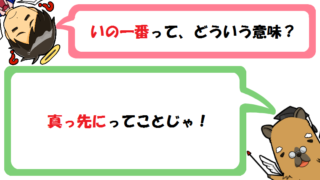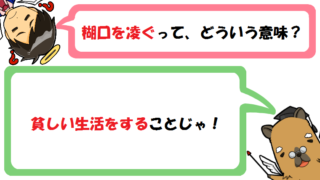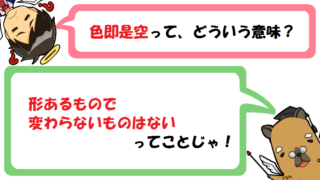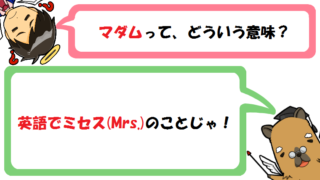めっぽう(滅法)の意味とは?語源(由来)は仏教?滅法界や盲滅法も!滅法の読み方は?めっぽう意味はめっちゃ?めっぽうかい(滅法界)は、めっぽうと同じ意味?盲滅法(めくらめっぽう)って?めっぽうの語源(由来)は仏教用語?めっぽうの類義語はあるの?めっぽうの使い方も例文で紹介します!
もくじ
めっぽう(滅法)の読み方と意味とは?

「喧嘩にはめっぽう強い」
「お酒にはめっぽう弱い」
といいますが、どのような意味なのでしょうか?
今日は、めっぽうについて解説していきましょう\(^o^)/
程度がはなはだしいこと。
並々でないこと。
度が外れていること。
まず、滅法の読み方は「めっぽう」です。
国語辞書には、道理に合わないことや、常識を超えている様子と書いてありますが…めっぽうを簡単にいえば、「とても」です。
「喧嘩にはめっぽう強い」→「喧嘩がとても強い」
「お酒にはめっぽう弱い」→「お酒にとても弱い」
というわけです。
大層、法外、無茶苦茶、けた外れなどと言い換えることもできますね。
めっぽうかい(滅法界)は、めっぽう(滅法)と同じ意味
 参照:http://www.asahi.com/special/kotoba/archive2015/danwa/2010102600009.html
参照:http://www.asahi.com/special/kotoba/archive2015/danwa/2010102600009.html
大正時代のカルピスのポスターに、「めっぽうかいにうまい」と書いてありましたが、漢字では「滅法界」です。
「滅法界」も、めっぽうと同じ意味で、「とても」という意味です。
つまりカルピスは「この世のものとは思えないほどおいしい」ということですね。
おそらく、カルピス株式会社の三島海雲さんは僧侶だったので、このキャッチコピーを思いついたのでしょう。
盲滅法(めくらめっぽう)とは?
盲滅法は、何の見当もつけずに、やみくもに事を行うことです。
読み方は「めくらめっぽう」で、「もうめっぽう」ではありません。
めっぽう(滅法)の語源(由来)は仏教?

めっぽうは漢字で「滅法」と書き、仏教用語が由来です。
めっぽう(滅法)とは、因縁に支配される世界を越えた、絶対的な不変の真理のことです。
仏教では、全てのものの存在には「因縁」の法則があると考えられていますが、時には「その法則が消滅する」ことがあり、それが「滅法」というわけです。
「因縁を超越した絶対的なもの」という意味から、「はなはだしい・度を越した・並はずれた」という意味で使われるようになりました。
めっぽう(滅法)の類義語は?
ここでは、めっぽうの類義語を紹介します\(^o^)/
すこぶる、きわめて、めっきり、たいへん、
非常に、かなり、いたく、なにより、とても、
ずいぶん、はなはだ、大層、実に、まことに、
誠に、大変、ひどく、飛びきり、めっちゃ、
ずば抜けて、飛び抜けて、法外に、すごく、
けた外れに、おそろしく、滅茶苦茶、
無茶苦茶、とてつもなく、など
めっぽう(滅法)の使い方を例文で紹介!

めっぽうは、程度ははなはだしいことを表す言葉でしたね。
非常に・きわめて・とてもなどと言い換えると理解しやすいかと思います。
めっぽうは、「弱い・強い・暑い・寒い」などの程度が、けた外れだと言いたいときに使われます。
良いことにも悪いことにも使えますが、良いことに使われることが多いです。
それでは、めっぽうの使い方を例文で見ていきましょう\(^o^)/
「彼は喧嘩がめっぽう強い。」
「私は雪国で育ったためか、暑さにはめっぽう弱いのです。」
「彼女はパソコンやスマホにはめっぽう疎いのだった。」
「お金のかかる趣味にハマり、残金がめっぽう減るようになった。」
「子供は、本を読むのがめっぽう好きだ。」
「怖い話はめっぽうダメだ。」
めっぽうについて、最後まで読んでいただきありがとうございました!
「○○にはめっぽう強い!」と言えるようになりたいですね。