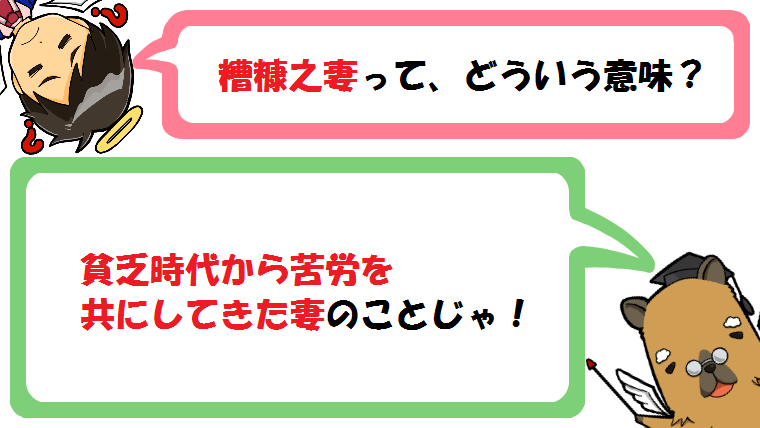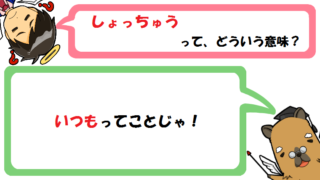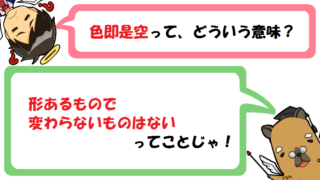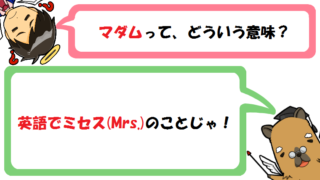糟糠之妻の意味とは?由来(語源)は後漢書?使い方を例文で紹介!糟糠之妻の読み方は「そうこうのつま」!糟糠之妻の意味とはどんな妻?糟糠の妻は堂より下さずって?糟糠之妻の由来(語源)は後漢書?糟糠之妻の類義語は?糟糠之妻の英語は?糟糠之妻の使い方も例文でわかりやすく紹介します!
糟糠之妻の読み方と意味とは?どんな妻?

今日は、糟糠之妻について解説していきましょう\(^o^)/
読み方は「そうこうのつま」。
「糟糠の妻」とも呼ばれる。
貧しいときから共に連れ添って、苦労を重ねてきた妻のこと。
まず、糟糠之妻の読み方は「そうこうのつま」です。
「糟糠の妻」とも言います。
「糟」は酒粕(さけかす)、「糠」は米糠(こめぬか)のこと。
酒粕は酒を造るときに出る残りかす、米糠は玄米を精白するときに出る粉です。
「糟」も「糠」も元々は捨てるもので、粗末な食べ物を表しています。
つまり、糟糠之妻とは、粗食を食べないといけないような貧しい時代から、一緒に苦労を分かち合ってきた妻のことです。
貧乏なときから連れ添ってくれた妻、という夫側からの感謝の気持ちが含まれている言葉ですね。
糟糠の妻は堂より下さず
糟糠之妻は、「糟糠の妻は堂より下さず(そうこうのつまはどうよりくださず)」の言い回しで、「糟糠の妻を追い出すことはしない」という意味でもよく使われます。
無名の貧しい頃から苦労を共にしてきた妻は、自分が出世して有名になっても別れたりしてはいけないという教訓ですね。
糟糠之妻の由来(語源)は後漢書?

糟糠之妻の語源は、昔の中国の書物「後漢書 宋弘伝(ごかんじょ そうこうでん)」の以下の文章が由来です。
白文:糟糠之妻不下堂
書き下し文:糟糠の妻は堂より下さず
現代語訳:貧しい生活を共にしてきた妻を表座敷から下ろしてはいけない
中国の後漢の時代。
後漢王朝の初代皇帝「光武帝」と家臣の「宋弘」がいました。
光武帝は、宋弘の高い身分に似合うように、妻を変えて自分の姉と結婚するように促しました。
しかし、宋弘は「貧乏だった頃の友人を忘れたり、貧しいときから連れ添った妻を離縁したりするなどできません。」と言って断りました。
糟糠之妻の類義語は?
糟糠之妻の類義語は、「宋弘不諧(そうこうふかい)」と「糟粕之妻(そうはくのつま)」です。
「宋弘不諧」も「糟粕之妻」も、上記の故事から生まれた四字熟語です。
糟糠之妻の英語は?

糟糠之妻は、英語では「貧乏な頃から支えてくれた妻」などと言い換えて表現しましょう。
「one’s wife married in poverty」
「a wife who has shared one’s poverty」
「wife who has followed one through hard times」
糟糠之妻の使い方を例文で紹介!

糟糠之妻とは、貧しくて苦しかったことから、連れ添ってきた妻のことでしたね。
夫が昔のことを振り返って、貧乏な時期から支えてくれた妻に感謝する場面で使われることが多いです。
また、夫以外の第三者が糟糠之妻を使うのは、「粗末なものしか食べられない経済力」という意味になってしまい、大変失礼になります。
間違っても、結婚式で「糟糠之妻と素敵な家庭を築いてください」と使わないようにしましょう。
それでは、糟糠之妻の使い方を例文で見ていきましょう\(^o^)/
「長年連れ添った糟糠之妻を失ってから、毎日抜け殻のように過ごしている。」
「人気俳優になった途端、下積み時代を支えてきた糟糠之妻と離婚するなんてひどい話だ。」
「本日定年退職を迎えたが、苦楽を共にしてきた糟糠之妻には、感謝してもしきれません。」
「糟糠の妻は堂より下さずという通り、これからも妻を大事にしよう。」
「糟糠之妻を捨ててしまったが、復縁できないものか。」
糟糠之妻について、最後まで読んでいただきありがとうございました!
糟糠之妻はお金目当てではないので、信用できそうですね。