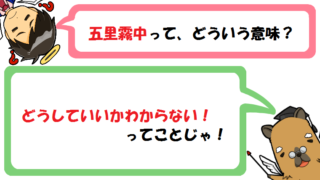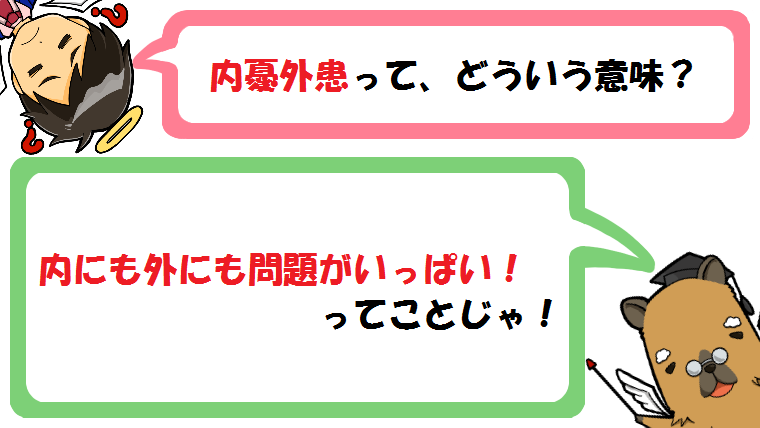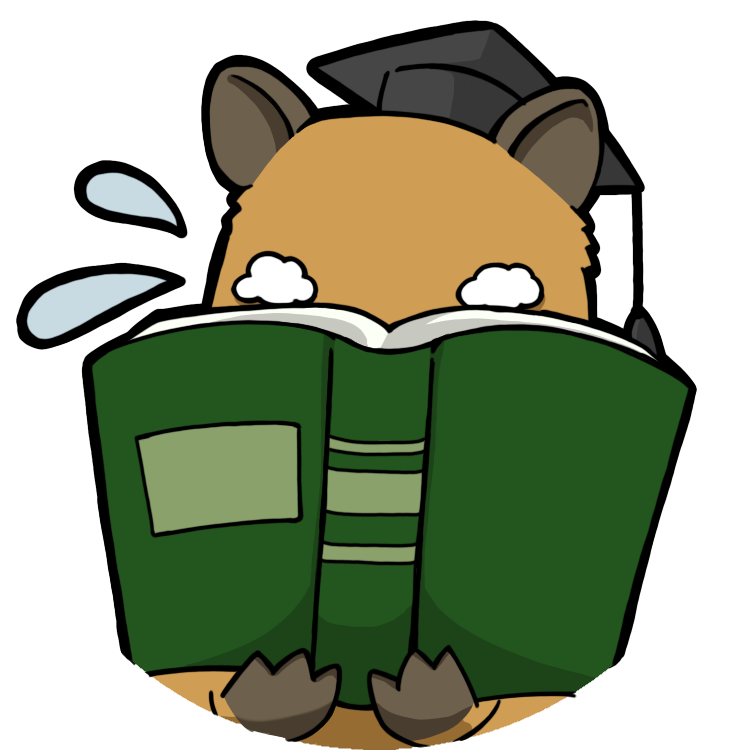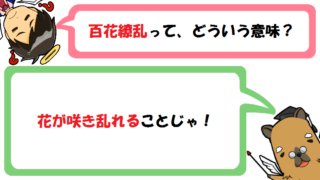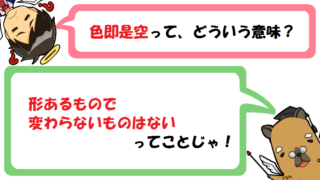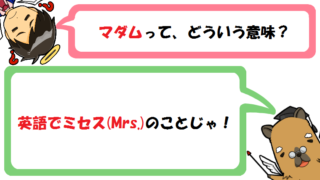内憂外患の意味とは?対義語/類語/英語は?使い方も簡単に解説!「内憂外患こもごも至る」内憂外患の意味と読み方は?内憂外患は「内にも外にも問題がいっぱい」ってこと!?内憂外患の由来は?内憂外患の類語・対義語・英語は?内憂外患の使い方(例文)を紹介!内憂外患について簡単に解説!
内憂外患の意味と読み方は?

「内憂外患こもごも至る」と新聞やニュースで見聞きすることがありますが、どのような意味なのでしょうか?
今日は、内憂外患について解説していきましょう\(^o^)/
読み方は「ないゆうがいかん」。
国内にも国外にも心配事や問題があること。
「内憂」は内側にある問題のことで、国の内部にある心配事のことです。
「外患」は外側にある問題のことで、外国との間に生じる災難のことです。
二つが組み合わさった「内憂外患」は、国の内部だけでなく、外部にも問題がたくさんあることという意味になります。
内憂外患は主に政治の場面で、「国政問題と外交問題の両方で苦戦中」のような状況に対して使います。
他にも、会社組織や家庭などの個人的な心配事にも内観憂慮が使われることがあります。
「内憂外患こもごも至る」という言い回しがよくされますが、これは「内外の問題がかわるがわる来る」という困った事態に陥っているわけですね。
内憂外患の由来は?

内憂外患の由来は、昔の中国の歴史書「春秋左氏伝 成公一六年」の中にある話です。
中国の春秋時代(575年)、晋の国と楚の国との間で起こった「鄢陵(えんりょう)の戦い」のときのことです。
晋の国の范文子(はんぶんし)という人物が、
「我々は理想的な君主ではないので問題を完全になくすことはできない。
外の問題が無くなれば、必ず国政に問題が出てくるものだ。
あえて楚の国を問題として残しておいて、国内の団結に利用しよう。」
と楚の国と戦わずに退却すべきだと主張しました。
この結果、「鄢陵の戦い」では晋の国が勝利したのです。
范文子のセリフの中の以下の文章が「内憂外患」の由来となりました。
「唯聖人能内外無患」
(ただ聖人のみよく内外患いなし)
→聖人だけが完全に内外の問題をなくせるのだ。
ただし、「内外無患」は「国内外に問題がない」という意味になってしまいます。
現実の世界では国内外の問題が山積みですから、「内憂外患」に派生したのです。
内憂外患の類語は?
内憂外患には、以下のような類語があります。
- 内患外禍(ないかんがいか)
- 内憂外禍(ないゆうがいか)
- 内患外憂(ないかんがいゆう)
これらは全て内憂外患と同じ「国内外に問題がある」という意味です。
内憂外患の対義語は?

内憂外患の対義語は、「国内外に問題がなく、平和」という意味の言葉になります。
読み方は「てんかたいへい」。
世の中が良く治まっていて、穏やかな様子。
読み方は「へいおんぶじ」。
何事もなく、穏やかな様子。
読み方は「ないへいがいせい」。
国内がよく治まり、外国との関係も良好なこと。
読み方は「ちへいてんせい」。
世の中が平穏に統治されていること。
内憂外患の英語は?

内憂外患は、英語でどのように表現すれば良いのでしょうか?
「be beset with difficulties both internal and external(内部と外部の両方の困難に悩まされる)」
「troubles both at home and abroad(国内と海外の両方の問題)」
「domestic troubles and external threats(国内の問題と外部の脅威)」
「calamities from within and without(内外からの大きな災難)」
「internal and external troubles(内部と外部の問題)」
内憂外患の「国内外に問題がある」というニュアンスを英語で出せるといいですね。
内憂外患の使い方(例文)を紹介!

内憂外患とは、国内の心配事や、外国との間に生じる厄介な出来事のことでしたね。
国・組織・家庭などの内外で解決しなければならない問題が山積みで頭を悩ませている状況を表す言葉です。
「消費税問題や外交問題など、内憂外患こもごも至る」
「仕事で内憂外患の問題が絶えず、頭を悩ませている」
「家でも会社でも心配事が山積みで、まさに内憂外患だ」
「社員の集団辞職と得意先との取引中止で、内憂外患の状況だ」
「江戸時代、徳川家慶が治めていた時代は、徳川斉昭から『内憂外患の時代』と呼ばれた」
「役職が上がってから、内憂外患の苦しみを味わっている」
「総理大臣は内憂外患を気にかけすぎて、身動きが取れなくなっている」
「最近は内憂外患の出来事ばかり起こる」
内憂外患について、最後まで読んでいただきありがとうございました!
難しい言葉ですが、ぜひ覚えておいてくださいね!