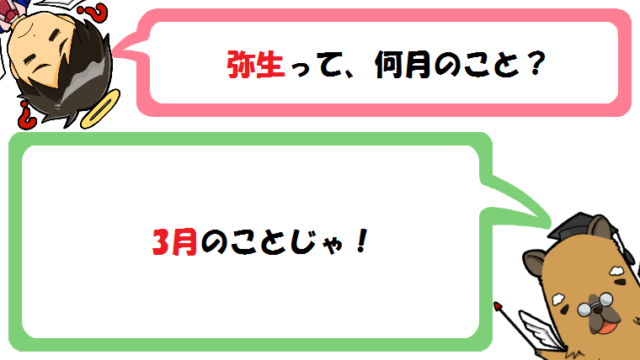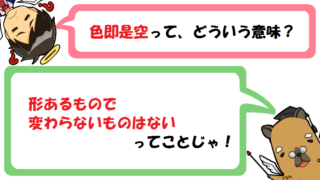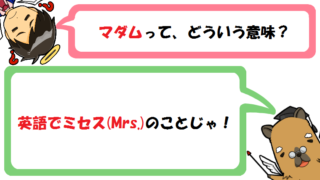神無月は旧暦の何月?意味/読み方/由来とは?出雲大社では神在月!?10月の時候の挨拶と季語も紹介!神無月の意味や読み方とは?神無月は旧暦の何月?神無月は現在の暦でいつからいつまでの時期?なぜ神無月なのか由来(語源)を解説!10月の季語と上旬・中旬・下旬の時候の挨拶も例文で紹介!
もくじ
神無月は旧暦の何月?読み方と意味は?

今日は、神無月について解説していきましょう\(^o^)/
読み方は「かんなづき」。
陰暦(旧暦)の10月のこと。
まず、神無月の読み方は「かんなづき」です。
「かみなづき」や「かむなづき」、「かみなしづき」とも呼ばれます。
神無月は、陰暦(旧暦)の10月を指す言葉です。
神無月を現在の暦に当てはめると、10月下旬~12月上旬ごろの時期になります。
便宜上、現在の暦の10月を「神無月」と呼ぶことがあります。
「陰暦」とは、月の満ち欠けの周期を基にした暦のことで、1ヶ月は約29.5日です。
日本では、明治6年に陽暦が採用される以前に陰暦が使われていたため、陰暦を「旧暦」と呼ぶ場合もあります。
ちなみに現在、日本を始めとした世界の多くの国で使われているのは「太陽暦」で、地球が太陽の周りを回る公転周期を基にした暦です。
日本では、太陽暦を「新暦」と呼ぶこともあります。

神無月は出雲大社では神在月!?

10月には、全国の八百万の神様が出雲大社(島根県出雲市)へ会議に出かけてしまうと言われています。
そのため、神様が出かけてしまう地方では「神無月」、反対に神様が集まってくる出雲の国では「神在月/神有月(かみありづき)」と呼ぶわけです。
しかし神様たちが出雲大社に集合して、一体何を会議するのでしょうか?
なんと、一年間の人の運命や誰と誰を結婚させるかなどの「縁結びの話し合い」をするのです!
遠く離れた場所の人と結婚するのは、会議の結果なのかもしれませんね♪
毎年旧暦10月11日~17日に出雲大社で会議が行われるとして、その期間に「神在祭(かみありまつり/かみありさい)」というお祭りが行われます。
神無月の特に神在祭の時期には、ご利益にあずかるために多くの人が出雲大社へ参拝しにくるので、大変混雑します。
ちなみに、伊勢神宮の神様は出雲大社の会議には参加しません。
出雲大社の大国主大神は国土を治める国津神(くにつかみ)ですが、伊勢神宮の天照大御神は天上界から地上に降臨した天津神(あまつかみ)です。
神無月に出雲大社に集まるのは国津神の系統の神様だけなのです。
神様にも種類があるのですね\(^o^)/
神無月の由来(語源)は?

神無月の「無」は、現代語で「の」にあたる連体助詞の「な」で、「神の月」という意味だとする説が有力です。
神無月は神を祭る月なので、まさに「神の月」なのです。
中世の俗説では、10月に全国の神々が出雲大社に集まり、各地に神がいなくなることから「神無月」になったとされています。
出雲の国(現在の島根県)では、反対に「神在月/神有月(かみありづき)」と呼ばれます。
他にも、
- 雷の鳴らない月で「雷無月(かみなしづき)」が由来の説
- 新穀で酒を醸す月なので「醸成月(かみなしづき)」が語源の説
があります。
10月の時候の挨拶と季語も紹介!

手紙に使える10月の時候の挨拶も紹介していきましょう\(^o^)/
時候の挨拶は季節を表す言葉を用いた文章のことで、相手の健康や安否を気遣う意味があります。
10月上旬~中旬の時候の挨拶
10月上旬~中旬の「時候の挨拶」+「安否の挨拶」の例文です。
仲秋は陰暦8月の異称ですが、秋の真ん中の意味なので、現代では白露(9月8日)の頃から寒露(10月8日)の前日頃までとされます。
<ビジネス向け>
「仲秋の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。」
「秋晴の候、〇〇様にはつつがなくお暮しのこと存じます。」
「紅葉の候、先生におかれましてはご健勝のこととお喜び申し上げます。」
「秋冷の候、貴社にはいよいよご盛栄のことと拝察いたします。」
<カジュアルに>
「学生たちが衣替えすると一気に街が秋づきます。皆様お変わりありませんか。」
「食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋…。どんな秋をお過ごしですか。」
「すがすがしい秋晴れがつづくこの頃です。お元気でいらっしゃいますか。」
「木々の葉も鮮やかに色づいてきました。いかがお過ごしですか。」
10月中旬~下旬の時候の挨拶

10月中旬~下旬の「時候の挨拶」+「安否の挨拶」の例文です。
朝晩の冷え込みがだんだんと強くなってくる時期ですね。
<ビジネス向け>
「紅葉の候、貴社のご発展心より嬉しく思います。」
「霜降の候、貴殿ますますご健勝の段、何よりと存じます。」
「秋冷の候、貴社にはいよいよご隆盛の趣、慶賀の至りに存じます。」
「錦秋の候、〇〇様にはお元気にお過ごしのことと存じます。」
<カジュアルに>
「実りの秋を迎え、すっかり食べ過ぎてしまいます。その後お元気にされていますか。」
「朝夕はだいぶ涼しく感じられるようになりました。お風邪など召されていませんか。」
「輝く月が美しい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。」
「落ち葉がはらはらと冷たい風に舞う季節となりました。お健やかにお過ごしのことと存じます。」
10月の季語は?

時候の挨拶は、季語を入れて季節感を出すのがマナーです。
10月の季語をいくつか紹介するので、手紙を書くときの参考にしてくださいね♪
秋寒、秋惜しむ、秋深し、朝寒、寒露、肌寒、晩秋、夜寒、露寒、
露霜、野山の色、稲刈、秋の空、秋晴れ、秋収め、秋時雨、秋の霜、
露時雨、猪、ツグミ、シギ、モズ、ムクドリ、ミノムシ、蜻蛉、きのこ、
きのこ狩り、秋刀魚、イチジク、柿、栗、ザクロ、金柑、銀杏、紅葉、
紅葉狩り、楓、菊、コスモス、桔梗、金木犀、木の実、松茸、林檎、
新米、運動会、体育祭、秋祭り、ハロウィン、ハイキング、体育の日、
文化の日、秋分の日、など
時候の挨拶は、その季節を感じられる言葉を選べば、どんな表現でも構いません。
ぜひ、季語を使ってあなたらしい時候の挨拶を作ってみましょう!
神無月について、最後まで読んでいただきありがとうございました!
健康にご留意し、味覚の秋や行楽の秋を存分にご満喫ください\(^o^)/