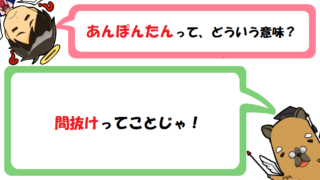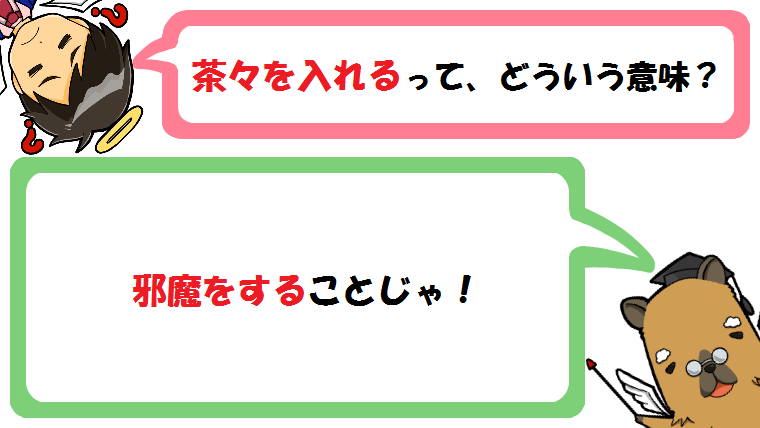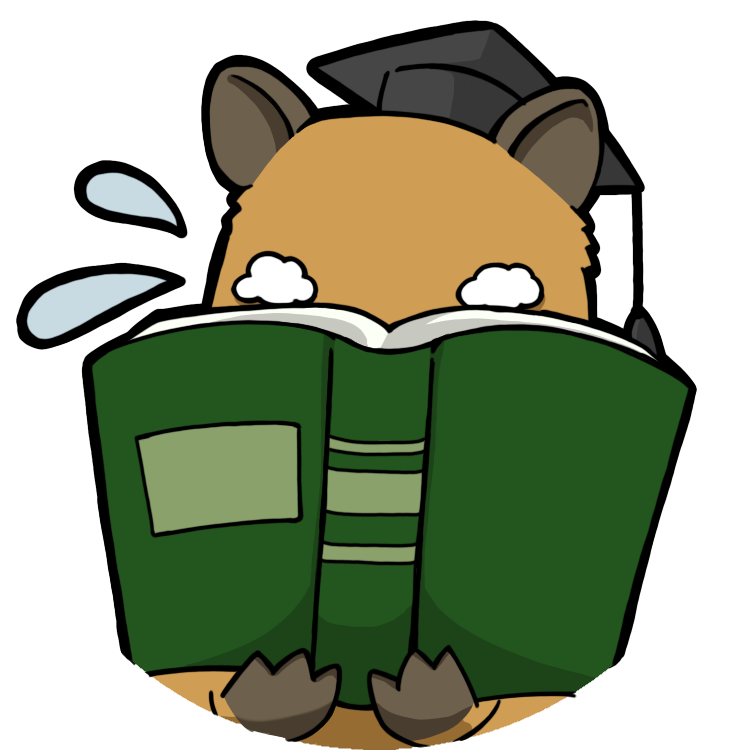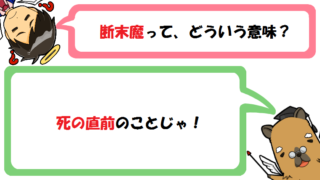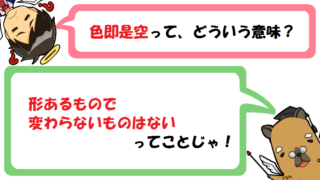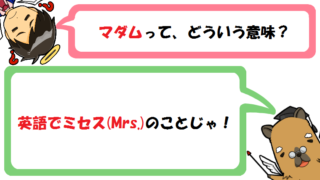茶々を入れるの意味とは?語源(由来)は淀殿?類語/英語/例文も紹介!茶々を入れるの語源(由来)は?豊臣秀吉の側室「淀殿(茶々)」が語源?「邪邪」が「茶茶」に転じた?茶を入れて一服することが由来?「茶」は当て字?茶々を入れるの類語と英語は?茶々を入れるの使い方(例文)も紹介!
もくじ
茶々を入れるの意味とは?
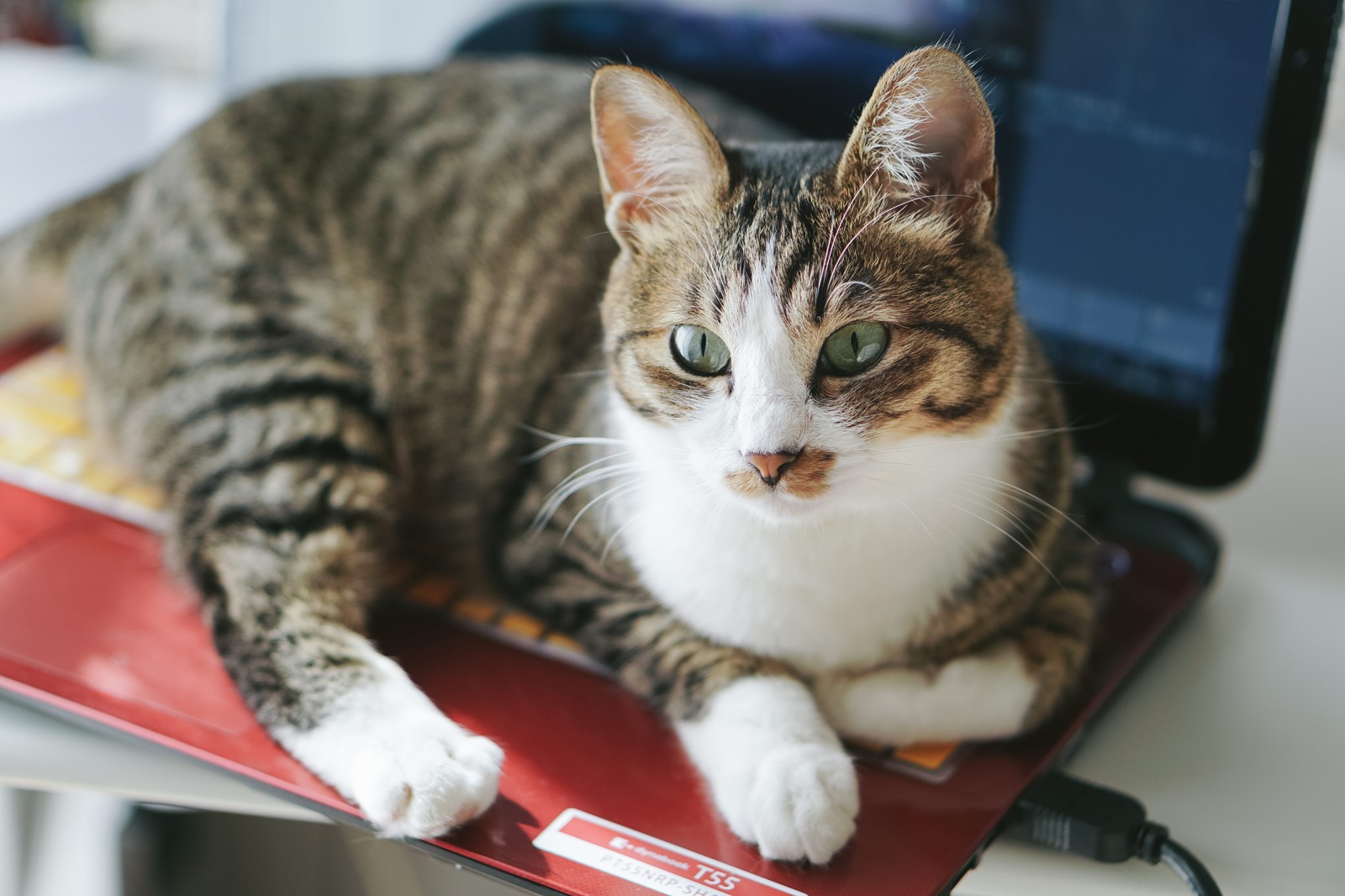
大事なところで「茶々を入れる人」っていますよね。
今日は、茶々を入れるについて解説していきましょう\(^o^)/
邪魔をする、水を差す
茶々を入れるとは、冷かして話を妨げることです。
「茶々を付ける」や「茶々が入る」とも使われます。
「茶々を入れる人」は、話の途中で横から口を挟んで、冷かしたり、引っ掻き回したりする面倒な人のことです。
意見がまとまりかけていたときに、空気を読まずに茶々を入れられるとツラいものがあります。
ポイントは、「邪魔をする」ということ。
良いタイミングで良いことを言う人は、茶々を入れる人ではありません。
茶々を入れるの語源(由来)は?
茶々を入れるの語源(由来)は、諸説あります。
豊臣秀吉の側室「淀殿(茶々)」が語源の説
 出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%80%E6%AE%BF
出典:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%80%E6%AE%BF
豊臣秀吉の側室である淀殿(よどどの)が、茶々を入れるの由来だとする説です。
淀殿の本名は「浅井 茶々(あざい ちゃちゃ)」と言います。
淀殿(茶々)は、父親が近江国の戦国大名「浅井長政」で、母親が織田信長の妹・「市」です。
つまり、二人の娘ということは、淀殿(茶々)は織田信長の姪にあたるのです。
豊臣秀吉は淀殿(茶々)の母親「市」に憧れていたとされています。
市の娘3人の中で、最も面影が似ていたのが淀殿(茶々)だったため、気に入って側室に選んだと言われています。
(さらに、織田信長の血を引いているともなれば、話は早い!)
しかし、淀殿(茶々)が豊臣秀吉の側室に「入った」ことで、豊臣家が滅亡するきっかけになってしまいました。
そのため、「茶々を入れる」は邪魔をするという意味になったと言われています。
「邪邪」が「茶茶」に転じた説
「邪邪」には、
- 無理にわがままを言ってねだること
- いたずらに騒ぎ立てる、暴れる
という意味があります。
「何度も繰り返して邪魔をする」
→「邪魔!邪魔!」
→「邪邪(じゃじゃ)」
→「茶茶(ちゃちゃ)」
→「茶々を入れる」
と転じたとする説です。
茶を入れて一服することが由来の説

茶々を入れるの「茶」は、お茶の意味であり、お茶を入れて一服することが由来だとする説もあります。
やっていることを中断してお茶を飲むことから、邪魔をするの意味になったと言われています。
「茶」は当て字の説
日本語の「ちゃ」という音の響きには、「乱れる」ような印象があります。
元々「ちゃちゃを入れる」という言葉があり、それに日本でなじみ深い文化である「茶」の漢字を当てたという説です。
今では、「茶」の漢字自体に、飲み物のお茶以外に、「いい加減なことを言ってからかう」の意味も含まれています。
例えば、「茶化す」は、冗談のようにしてからかうことですね。
茶々を入れるの類語は?

あざけたり、ふざけてからかったりするという意味の茶々を入れるの類語を紹介します\(^o^)/
水を差す
読み方は「みずをさす」。
物事がうまく進んでいるときに邪魔をすること。
水を差すとは、熱い湯に水を入れてぬるくすることから来ています。
仲の良い者同士を仲違いさせることにも使われます。
横槍を入れる
読み方は「よこやりをいれる」。
横から口を出して、人の話を妨害すること。
横槍を入れるとは、戦場で戦っている双方の横から、別の一隊が槍で襲い掛かってくることから来ています。
半畳を入れる
読み方は「はんじょうをいれる」。
他人の言動に非難やからかいの言葉をかけること。
半畳を入れるとは、芝居で役者の芸に不満があるとき、見物人が敷いている半畳を舞台に投げ入れたことから来ています。
他にも、茶々を入れるの類語には、「からかう・冷かす・小突く・おちゃらかす・おちょくる」などがあります。
茶々を入れるの英語は?

「茶々を入れる」の邪魔をする、冷かすというニュアンスの英語を紹介していきましょう\(^o^)/
「tease(からかう)」
「to make fun of(からかう)」
「interrupt(割り込む、さえぎる)」
「butt in(干渉する、横槍を入れる)」
「pour cold water on(水を差す)」
「throw cold water on(水を差す)」
他にも、「throw a wet blanket on」という表現がありますが、直訳で「濡れた毛布を投げ入れる」で、「水を差してしらけさせる」の意味です。
これは、火事があったときに、水を含ませた毛布を炎に覆い被せて消化したことに由来します。
炎が一気に消えるので、盛り上がっている場面を興ざめにするという意味で使われるようになりました。
茶々を入れるの使い方(例文)は?

茶々を入れるは、話の途中で冷やかし混じりの冗談を言って邪魔をするという意味でしたね。
最後に、茶々を入れるの使い方を例文で見ていきましょう\(^o^)/
「授業中にくだらない茶々を入れるな!」
「最近、大事な話をしていると子供が茶々を入れてくる。」
「友達がデートしているのを見かけたので、ちょっと茶々を入れてこよう。」
「せっかく受験勉強をしようとしていたのに、弟に茶々を入れられる。」
「横から茶々が入るので、やる気がなくなってしまった。」
「真面目に頑張っている人に、茶々を入れたくなるのが自分の悪い癖だ。」
茶々を入れるについて、最後まで読んでいただきありがとうございました!
茶々を入れるのは、ほどほどにしましょう。