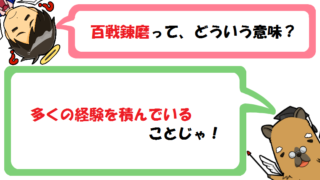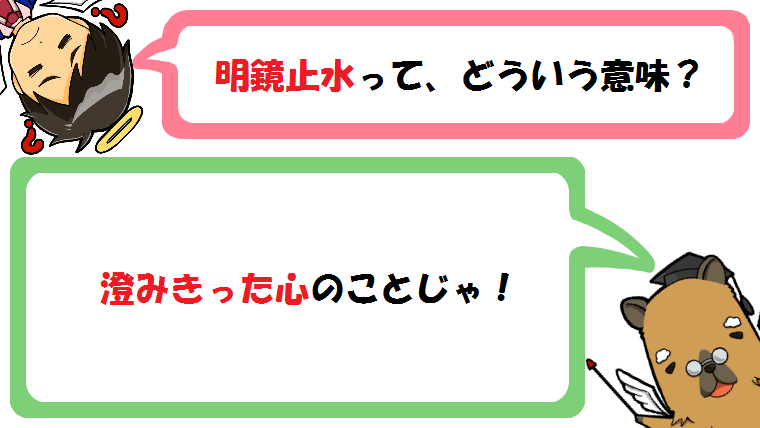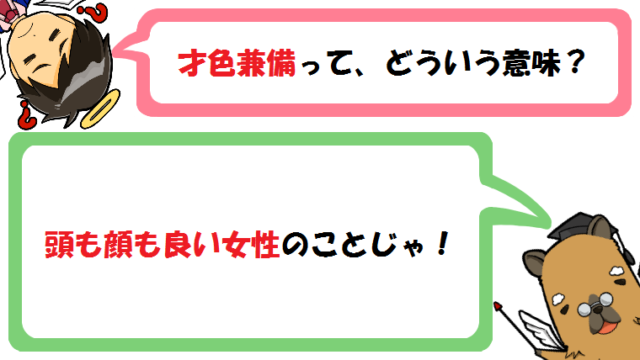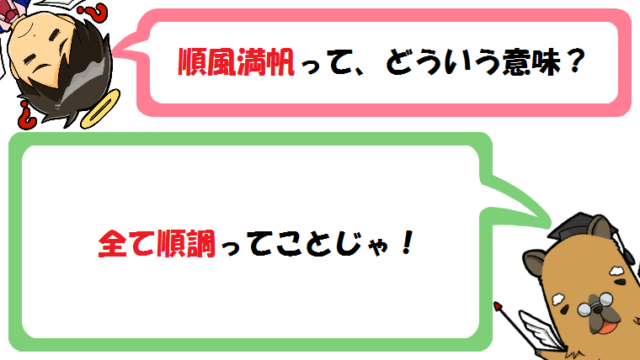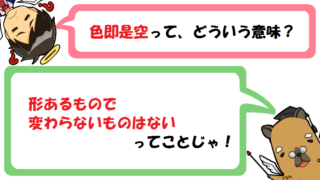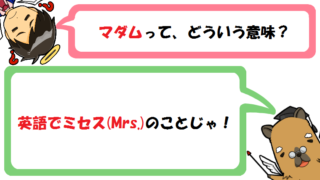明鏡止水の意味とは?由来(語源)は?類義語と対義語の四字熟語も!明鏡止水の読み方と意味とは?明鏡止水の心や明鏡止水の境地って?明鏡止水の由来(語源)は何?明鏡止水の類義語や対義語の四字熟語はあるの?明鏡止水は英語でどう表現すればいい?明鏡止水の使い方も例文で簡単に紹介します!
明鏡止水の読み方と意味とは?

「明鏡止水の心」や「明鏡止水の境地」と言いますが、どのような意味なのでしょうか?
今日は、明鏡止水について解説していきましょう\(^o^)/
何のわだかまりもなく、清らかで澄みきった心の状態。
まず、明鏡止水の読み方は「めいきょうしすい」です。
「めいけいしすい」とも読みます。
「明鏡」は一点のくもりもない鏡のことで、「止水」は波一つ立たない静かな水のことです。
明鏡止水とは、くもりのない鏡と静止している水のように、心にやましい点がなく、静かに落ち着いた心境をたとえた四字熟語です。
「明鏡止水の心」は、邪念がなく、明るく澄みきった心のことです。
また、わずかな動揺もなく落ち着き払っている心境を「明鏡止水の境地」と呼ぶこともあります。
ちなみに、剣道用語でも明鏡止水が使われています。
剣道では、心にさざ波が立てば相手の動きをとらえることはできません。
研ぎ澄ました鏡や澄みきった水のごとく、どんな小さなものをも心に映す「明鏡止水の心境」で相手の隙を見よということですね。
明鏡止水の由来(語源)は?

明鏡止水の由来は、昔の中国の書物「荘子 徳充符」になります。
「止水」は、その中の以下の文章が語源です。
<原文>
仲尼曰、人莫鑑於流水、而鑑於止水、唯止能止衆止。
<書き下し文>
仲尼曰く、人は流水に鑑みること莫くして、止水に鑑みる。唯だ止のみ能く衆止を止む。
<現代語訳>
孔子は、「人は流れる水を鏡として使うことはなく、静止した水を鏡とする。ただ止まった水のように静かな心を持った者だけが、社会の真の姿をとらえることができるのだ。」と言った。
上記の孔子の言葉は、足切りの刑を受けた人のところに、なぜか彼を尊敬して弟子入りをする人がたくさんいたため、弟子がその理由を尋ねた際の答えです。
穏やかで落ち着いた人の周りには、人が集まるということですね。
「明鏡」の語源は、同じく「荘子 徳充符」の以下の文章です。
<原文>
鑑明則塵垢不止、止則不明也、久与賢人処、則无過。
<書き下し文>
鑑明らかなれば則ち塵垢止まらず、止まれば則ち明らかならざるなり。久しく賢人とおれば、すなわち過ちなし。
<現代語訳>
鏡がきちんと磨かれていれば塵はつかない。
塵がつくのは、鏡が曇っているからだ。
立派な人と長く一緒にいると、心の曇りが取れて過ちがなくなるのだ。
ある先生のもとに弟子二人がいましたが、身分の高い一人がもう一人を見下していました。
見下された方の弟子が、「すばらしい先生と長く一緒にいるのに、まだ偏見という曇りは消えないのか…」と言ったのが「明鏡」の由来です。
ちなみに、昔の中国の思想書「淮南子 俶真訓」にも明鏡止水の言葉が見られます。
<原文>
人莫鑑於流沫、而鑑於止水者、以其靜也。
莫窺形於生鐵、而窺於明鏡者、以睹其易也。
夫唯易且靜、形物之性也。
<書き下し文>
人の流沫に鑑みる莫くして止水に鑑みるは、其の静かなるを以ってなり。
形を生鉄に窺う莫くして明鏡に窺うは、其の睹易きを以ってなり。
夫れ唯だ易かにして且つ静かなるは、物の性を形すなり。
<現代語訳>
人が泡立って流れる水を鏡とせず、静止した水を鏡とするのは、その水が静かであるからだ。
人がよく鍛えていない鉄に姿を映さず、明鏡に映すのは、その鏡が平らだからだ。
すなわち、ただひたすらに平らでかつ静かなものは、万物の本性をそのまま表すのだ。
明鏡止水の類義語の四字熟語は?

ここでは、明鏡止水の類義語の四字熟語を紹介していきましょう\(^o^)/
一片氷心(いっぺんひょうしん):濁りやけがれがなく、綺麗で澄んでいる心のこと
虚心坦懐(きょしんたんかい):何のわだかまりもないすなおな心で、物事にのぞむこと
虚静恬淡(きょせいてんたん):心静かでわだかまりがなく、さっぱりしていること
虚無恬淡(きょむてんたん):心に不信・不満・欲望などがなく、穏やかで落ち着いていること
光風霽月(こうふうせいげつ):心が澄んで、何のわだかまりもなく、爽快であること
心頭滅却(しんとうめっきゃく):心を無にして、無念無想の境地に達すること
晴雲秋月(せいうんしゅうげつ):心に汚れがなく、澄みとおっていること
則天去私(そくてんきょし):小さな私にとらわれず、身を天地自然にゆだねて生きて行くこと
大悟徹底(たいごてってい):すべての迷いを打ち破り、煩悩を離れて悟りきること
八面玲瓏(はちめんれいろう):心が清らかで、何のわだかまりもないこと
無想無念(むそうむねん):一切の邪念から離れて、無我の境地に到達した状態のこと
無念無想(むねんむそう):すべての邪念を離れて、無我の境地に達した状態のこと
明鏡止水を簡単な言葉で言い換えると、「明るい・一点の曇りもない・澄みきった」などになりますね。
明鏡止水の対義語は?

明鏡止水の対義語は、「清らかでない」や「濁った心」の意味を持つ言葉になりますね/(^o^)\
意馬心猿
読み方は「いばしんえん」。
欲情がどうにも抑えにくいこと。
意馬心猿は、煩悩や情欲のために、心が混乱して落ち着かないことです。
走り回る馬や騒ぎたてる猿を鎮めるのは容易ではないことから来ています。
疑心暗鬼
読み方は「ぎしんあんき」。
一度疑い始めると、何でもないことまで怖いと思ったり、疑わしいと感じたりすること。
「疑心」は疑いの心、「暗鬼」は暗闇の中の亡霊のことです。
疑いの心があると、暗闇の中にいるはずのない亡霊の姿まで見えるようになることから来ています。
焦心苦慮
読み方は「しょうしんくりょ」。
色々なことを心配して、考え苦しむこと。
「焦心」は気をもむことで、「苦慮」は心を悩まし考えることです。
焦心苦慮とは、色々な心配事で、焦っていら立つことを表します。
明鏡止水の英語は?
明鏡止水は英語でどう表現すればよいのでしょうか?
「a stable and clear state of mind(安定して澄みきった状態の心)」
「clear and serene(澄みきって穏やかな)」
<例文>
「His mind is clear as a mirror and pellucid as a lake.(心は明鏡止水の如し。)」
「My mind is as bright and clean as a stainless mirror.(私の心は明鏡止水だ。)」
「as a polished mirror and still water(磨かれた鏡や穏やかな水のように)」とつけると、明鏡止水の説明になります。
明鏡止水の「清らかで澄みきっている」というニュアンスを英語で出せるといいですね。
明鏡止水の使い方(例文)を紹介!

明鏡止水とは、曇りのない鏡と澄んだ水面のように、何の邪念もなく、安らかに落ち着いた心境を表す四字熟語でしたね。
何事にも惑わされず、動じない様子を表現するときや、静かで落ち着いた気持ちを表すときに使われます。
それでは、明鏡止水の使い方を例文で見ていきましょう\(^o^)/
「彼女は先入観を持たず、明鏡止水の心で判断している」
「全ての欲を断ち切って、明鏡止水の境地に達した」
「明鏡止水の心境で書道をする」
「退職後は明鏡止水のごとく穏やかに生活したいものだ」
「家族とのわだかまりを解いて、明鏡止水の気持ちで余生を過ごそう」
明鏡止水について、最後まで読んでいただきありがとうございました!
座右の銘にもぴったりの四字熟語ですね!